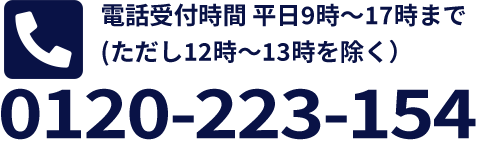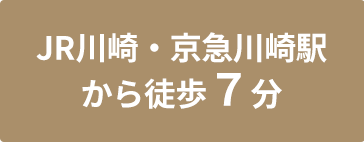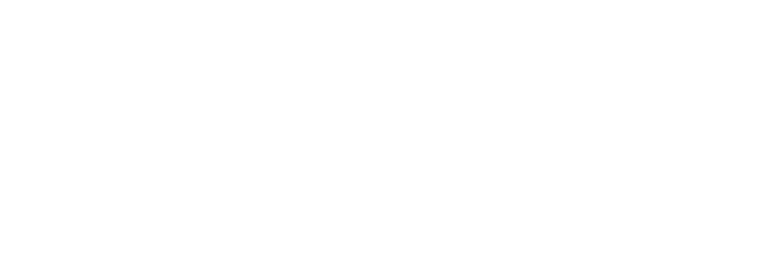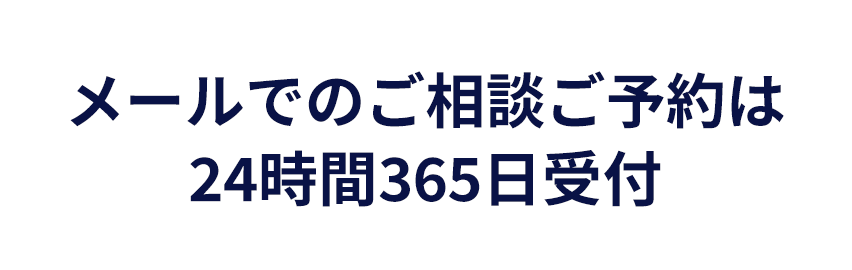共有持分放棄による共有の解消
はじめに
共有不動産について次のようなお悩みはないでしょうか?
- ・田舎にある共有不動産について、なぜか私が共有者の代表に選ばれてしまい、役所から固定資産税の納税通知や除草するよう連絡がくる。不動産業者に相談しても、価値のない土地で売却は無理だと言われてしまい、途方に暮れている。
- ・かなり前に亡くなった祖父名義の不動産があるが、私にも共有持分があるらしく、毎年、他の相続人から固定資産税の一部の負担を求められている。他の相続人に共有持分の引取をお願いしたが、誰も見向きもしない。業者に共有持分の買取りを依頼したが断られてしまった。
では、他の共有者が誰も引き取らない、買取業者に相談しても値段がつかないような価値のない共有不動産の共有関係を解消するためにはどうしたらよいでしょうか?
価値のない不動産の共有を解消する1つの方法として、共有持分を放棄する方法があります。不動産の共有持分は、他の共有者の承諾を得る必要はなく、単独で放棄をすることができます。そして、放棄された共有持分は他の共有者に帰属することになります。では、具体的にどのような手続きで共有持分の放棄をすれば良いのか、以下、手続きの流れを説明します。
手続きの流れ
他の共有者への通知
まずは、共有持分の放棄の意思を明確にするため、また、登記手続きのために、他の共有者に対して、共有持分を放棄すること及び放棄した共有持分の引取登記手続に協力するよう要望する旨の通知を送付します。この通知は、裁判上でも利用する証拠となるので、内容証明郵便で通知をすることが多いです。
他の共有者が、任意に登記手続きに協力してくれる場合は、登記手続きをして共有持分放棄の手続きは完了となります。
登記引取請求訴訟
他の共有者が任意に登記手続きに協力してくれれば良いのですが、協力してくれない場合や回答がない場合は、他の共有者を被告として、裁判所に登記引取請求訴訟を提起します。
この訴訟は、あまり争われることなく終わるケースが多いです。共有持分放棄の意思表示自体は、被告も争いようがない事案が多いので、裁判上で和解が成立する場合もあります。
裁判上で和解が成立したり、勝訴判決が出たりした後は、和解調書や確定判決に基づき登記手続きをして、共有持分の放棄の手続きが完了となります。
最後に
共有持分放棄の手続きは、共有者の人数が多く、事務手続きが相当な分量になるケースが多いです。だからといって放置すると、共有者がどんどん他界していき、不動産の共有者が益々増えていきます。今、検討しないといけないのは、この手続きを自分の子供たちや孫たちの世代にやらせて良いのか?子供や孫の世代にツケを回してしまうと、共有者の数が膨大な数になり、時間と費用がかなりかかることになります。子孫に負担をかけたくない、ご自身の世代で共有持分の放棄により共有状態を解消したいと考えている方は、是非、一度、川崎ひかり法律事務所にご相談ください。