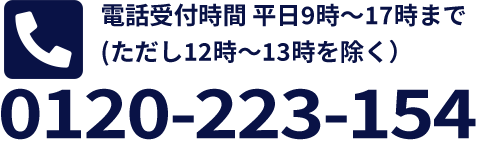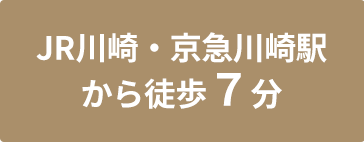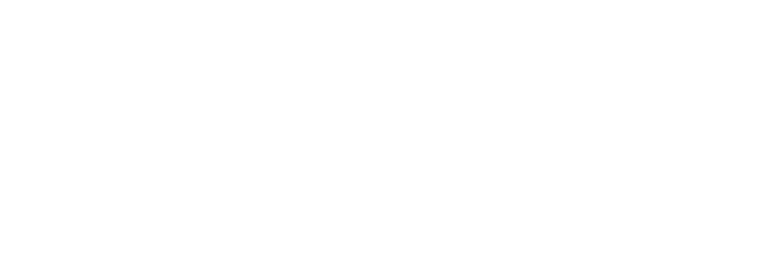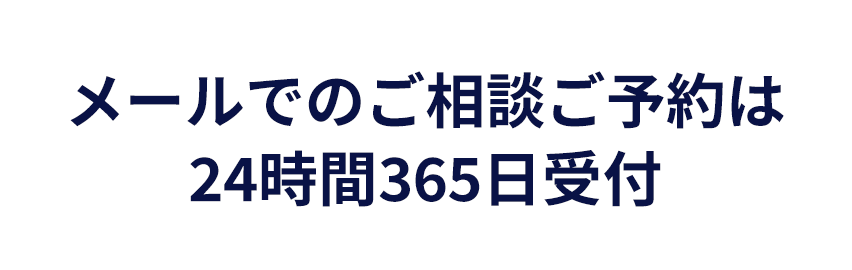管理費滞納トラブル
はじめに
マンションの各部屋の所有者は、「区分所有者」と呼ばれ、区分所有者で組織される管理組合に対し、管理費・修繕積立金など(以下「管理費等」といいます。)を支払わなければなりません。この管理費等の滞納問題が、最も管理組合様や管理会社様からの相談が多いトラブルとなります。回収のために取り得る方法も多岐に渡ります。個々の事件の具体的な状況により、回収方法は異なってきますので、一度、法律相談を実施の上、ベストな回収方法を提案させていただいております。以下、管理費等の滞納問題で、代表的な解決手段を順番に説明いたします。(以下の説明では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」と表記します。)
内容証明郵便等の督促
弁護士名義で内容証明郵便等において督促をすることが考えられます。解決手段としては一番簡単な手続きとなります。
これで無事に滞納管理費等を支払ってくれれば良いのですが、支払ってくれない場合は、裁判所を利用した法的手段を検討することになります。
支払督促
簡易裁判所に申立を行い、裁判所書記官が支払督促を相手方に送付することにより、滞納管理費等の支払いを促す手続きとなります。
メリットとしては、書類審査のみで、通常訴訟のように裁判所に出頭する必要がありません。また裁判所の手数料も通常訴訟の半額ですみます。相手方が支払督促に異議を申し立てない場合は、支払督促に仮執行宣言を付してもらうことで、強制執行をすることができるようになります。
デメリットとしては、相手方に書類を送付できることが前提の手続きとなるので、相手方が行方不明の場合は利用できません。また、相手方が異議を出した場合は、通常訴訟に移行してしまうので、初めから通常訴訟を利用した場合に比べて、費用・時間・労力がかかってしまうというリスクがあります。
民事訴訟
滞納管理費等の請求を求めて裁判所に訴訟提起します。基本的には月に1回程度の頻度で裁判期日が開催され、裁判が進行していきます。
メリットとしては、裁判の途中で和解が成立する場合もあり、その場合は、強制執行をしなくとも任意に支払ってもらうことが期待できます。また、裁判の審理が終了し判決となった場合、判決に基づき強制執行をすることができます。
デメリットとしては、相手方が争ってくる場合は、第一審だけでは終わらず、第二審(控訴審)、第三審(上告審)と3つの裁判所で審理される可能性があり、そうなると時間・費用・労力がかかってしまいます。(※もっとも、滞納管理費等の訴訟の場合は、相手方が支払義務そのものを争うことはほとんどなく、一括で支払えないので分割で和解したいとの申し入れがなされることが多く、控訴審や上告審まで争われることは、経験上、ほとんどありません。)
先取特権に基づく担保不動産競売申立
管理費等については、区分所有法7条に基づき、区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権という法定担保権があります。この先取特権に基づき、相手方が所有する区分所有建物の競売を申立てることができます。
メリットとしては、支払督促で仮執行宣言を付してもらったり、民事訴訟で判決を得たりしなくとも、いきなり区分所有建物について競売の申立ができることです。また、競売で落札されたら、競売の代金から滞納管理費等の回収ができますし、区分所有者も落札者に変更となるので、管理組合様としては、滞納するような資金繰りの悪い区分所有者とお別れすることができます。
デメリットとしては、申立には一定の要件があり、建物に備え付けた動産から回収することはできないのか、回収できるのであれば建物に備え付けた動産から先行して回収しなさい(動産執行・動産競売の申立て)というルールがあります。管理組合様に余計な費用を支出させないためにも、建物に備え付けた動産からは回収できないことを裁判所に説明し、担保不動産競売の申立てをスムーズに行うことが、弁護士としては腕のみせどころとなります。
また、裁判所に納める予納金の金額が高額(東京地裁管轄の場合で80万円以上)ですので、まとまった資金が必要となります。
そして一番の問題は、区分所有建物に住宅ローンなどの抵当権が設定されていて、無剰余取消しにならないかです。無剰余取消しとは、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないときに、競売手続きが途中で終わってしまうことです。無剰余取消しになると、それまでにかかった手続費用は全て申立人の負担になってしまうばかりか、滞納管理費を1円も回収できません。住宅ローンの被担保債権額が不明であることが多く、無剰余取消しについての正確な予測は困難です。予測は困難だけどやってみないと前に進まないといったケースも多々あります。
不動産強制競売申立
基本的に、仮執行宣言付支払督促や民事訴訟で判決を取得した後に、不動産強制競売の申立てを検討することになります。
メリットとしては、競売により落札されれば、競売代金から滞納管理費を回収できるだけでなく、滞納者は区分所有権を失い、落札者が新たな区分所有者になるので、滞納者とお別れできることです。
デメリットとしては、担保不動産競売とほぼ同様で、裁判所に納める予納金の金額が高額であることや無剰余取消しのおそれがあげられます。
59条競売
不動産強制競売や担保不動産競売でも無剰余になり滞納管理費等を回収できない場合(回収見込みがない場合も含む)は、最終手段として区分所有法第59条に基づく競売請求(以下「59条競売」と表記します。)を検討します。59条競売とは、競売手続により区分所有権を剥奪する手続きで、かなり厳しい要件をクリアする必要があります。
メリットとしては、不動産強制競売や担保不動産競売とは異なり、無剰余取消しがないと解釈されているので、滞納者は区分所有権を失い、競落人に区分所有権が引き継がれます。そのため、滞納するような資金繰りの悪い区分所有者とお別れすることができ、かつ、新たな区分所有者から滞納管理費等を回収できます(区分所有法第8条参照)。
デメリットとしては、59条競売はいわば最終手段であり、滞納者の区分所有権を剥奪してしまうことになるので、その要件がかなり厳格に定められています。
まずは、59条競売の要件として、滞納管理費等の金額等が、共同生活上の障害が著しいといえるのかが問題となりますが、滞納管理費の金額やマンションの規模により、要件該当性の見通しを付ける必要があります。そのため、管理費等を滞納しているからといって、あらゆる事案で59条競売ができるわけではありません。
次に、59条競売の要件として、任意交渉や通常の強制執行手続きで回収見込みがないのかが問題となります。
それらの要件を充足していたとしても、手続き上、更に厳格な要件が規定されています。まず、59条競売のためには、管理組合の総会で、滞納している区分所有者に弁明の機会を与えた上での特別決議が必要です。次に、総会の特別決議に基づき訴訟を提起して59条競売請求を認容してもらわないといけません。そして、59条競売請求の認容判決が確定したときから半年以内に59条競売の申立をするといった流れになります。また、事案によっては競売での落札者の手配が必要になることもあります。いずれにせよ、かなりの時間・労力・費用がかかる手続きであることは間違いありません。
この厳格な59条競売請求をするためには、経験のある弁護士に依頼することが必須だと思われます。
最後に
これまで説明したとおり、滞納管理費等の回収については、その事案ごとに適切な見通しや方針を立てることが必要となります。滞納管理費問題でお困りの管理組合様・管理会社様は、是非、一度、川崎ひかり法律事務所にご相談ください。
よくある相談(Q&A)
区分所有者が専有部分で孤独死してしまいました。管理費等の滞納がどんどん嵩んでしまっている状況です。管理費等は誰に請求したらよいでしょうか?
A:亡くなった区分所有者の相続人を調査する必要があります。相続人が判明したら、相続人に対して滞納管理費等を請求します。場合によっては、相続人が全員相続放棄してしまうこともあります。その場合は、相続財産清算人を選任して滞納管理費等の請求をすることもあり得ます。
区分所有者が行方不明で連絡が取れず、管理費等をかなり滞納しています。どうしたらよいでしょうか?
A:区分所有者の所在調査をします。所在調査で行方が分かれば良いのですが、どうしても行方が分からない場合は、不在者財産管理人の選任申立をして、不在者財産管理人に対して管理費等を請求することもあります。
登記名義上の区分所有者がすでに亡くなっている様子で、専有部分にはお孫さんが居住しています。管理費等が滞納になっていて、誰に請求すれば良いのでしょうか?
A:登記名義上の区分所有者の相続人調査をして、相続人に対して滞納管理費等を請求していきます。居住しているお孫様の協力が得られる場合は、お孫様から家族関係に関する情報を得たり、相続人らに対し登記名義の変更や滞納管理費を支払うよう促してもらったりして、迅速に解決ができるケースもあります。
滞納管理費等の請求を弁護士に依頼した場合、弁護士費用等の請求ができますか?
A:標準管理規約に準拠した管理規約であれば、違約金として弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求することができます。