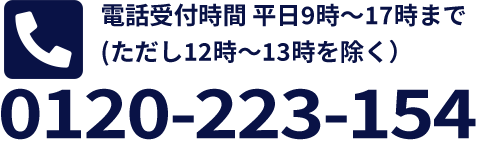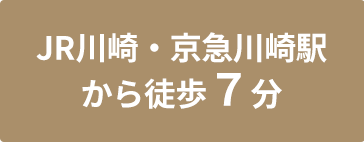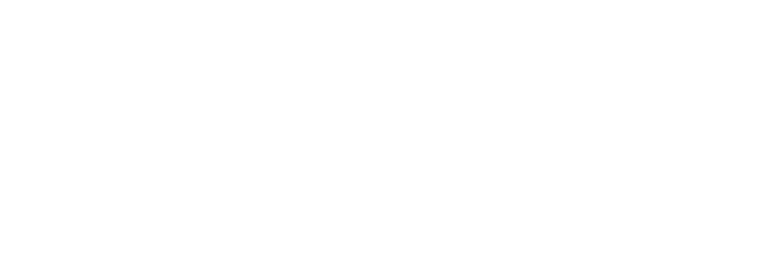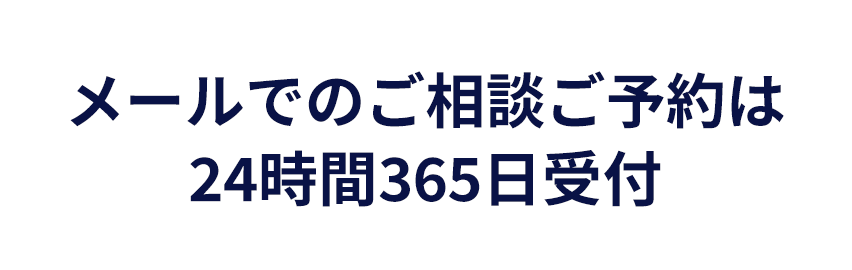共有物分割請求訴訟による共有の解消
共有物分割訴訟における共有物分割の方法
共有物分割請求訴訟における分割方法には、①現物分割、②賠償分割(全面的価格賠償)、③競売分割(換価分割)の3種類の方法があります。以下、これらの方法を説明します。
現物分割
不動産が物理的に分割可能な場合、各共有者の持分に応じて土地や建物を分ける方法を現物分割といいます。
しかし、物理的な分割は、たとえば1つの家屋や狭い土地のような状況では難しいため、現実的には適用されないケースが多いです。広大な土地であれば一部を切り離して所有することが可能かもしれませんが、多くの場合、建物や住宅地では現物分割ができません。
賠償(代償)分割(全面的価格賠償)
共有者の一人が他の共有者の共有持分を買い取って、賠償金(代償金)を支払い、不動産を単独所有にしてしまう分割方法を代償分割といいます。
裁判で代償分割が認められるためには次の要件を満たす必要があります。
- ①共有物のすべてを特定の共有者が取得する相当な理由があること
- ②特定の共有者が代償金を支払う能力があること
- ③取得持分の価格が適正に評価されていること
- ④共有者間の実質的公平を害さないこと
競売分割(換価分割)
現物分割や賠償(代償)分割が困難な場合、補充的な方法として競売手続きによって共有不動産を強制的に分割することになります。これを競売分割(換価分割)といいます。具体的な手続きの流れとしては、裁判所は、現物分割や賠償(代償)分割が困難な場合、不動産の競売を命じる判決を下します。その後、当該判決に基づき、裁判所に不動産の競売を申立てることになります(この競売を「形式競売」と呼びます。)。そして形式競売によって共有不動産を第三者に売却し、その売却代金を共有持分に応じて各共有者に分配することになります。
この競売分割のメリットとしては、他の共有者の意思にかかわらず、強制的に不動産の共有状態が完全に解消され、共有者間での争いも解決することができます。デメリットとしては、競売代金が、通常の不動産評価額の相場より低額になるリスクがあり、共有者全員が経済的な損失を被ることがあります。
おわりに
共有物分割請求訴訟には、裁判上認められている分割方法と各要件といった専門知識が必要となります。そして、各要件をどのように立証していくかなどの訴訟戦略が求められます。そこで、共有物分割訴訟を検討されている方は、是非、一度、川崎ひかり法律事務所にご相談ください。