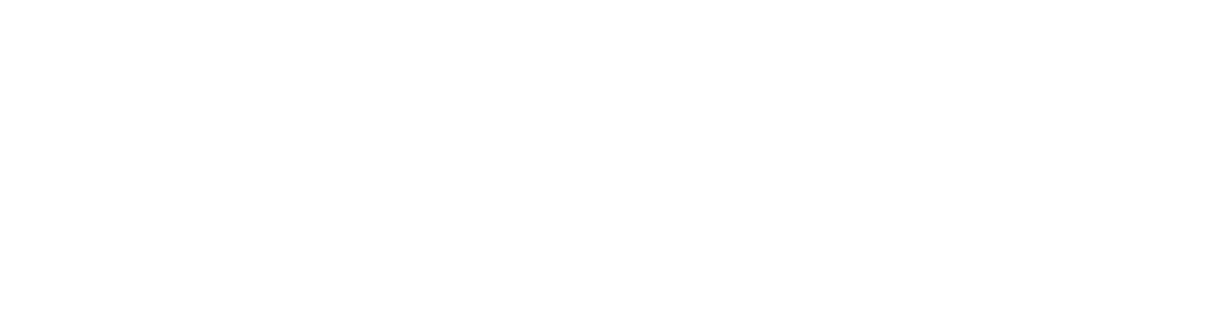依頼者Xさんは、長年、被相続人である妻Aと2人暮らしを続けていましたが、約3年前に被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは、生前、消費者金融から数十万円の借入れをしていましたが、当時、Xさんはそのような借入れの事実を知りませんでした。
その後、Xさんは、自宅の固定電話に、上記金融機関から連絡があったことで、被相続人Aが借入れを行っていたことを知りました。
そして、Xさんは、金融機関から「相続したのであれば、債務を支払ってほしい。」と言われましたが、返済資力にも乏しく、対応に苦慮してしまったため、当事務所にご相談に来られました。
被相続人が亡くなった約3年後に相続放棄が認められた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:夫
被相続人Aによる借入れの事実など一切知らず、返済資力もなかったことから、支払いに応じない手段はないかとご相談されました。
相続が生じた場合、原則として、相続が開始したこと等を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません(このような期間を、「相続放棄申述期間」と言います。)。
もっとも、例外的に、相続放棄申述期間を伸長できる場合が存在するため、弁護士は、そのような申述期間の伸長が認められる場合にあたることを主張して、裁判所に相続放棄を認めてもらうための活動を行いました。
本件では、主に、被相続人Aには生前、プラスもマイナスも含め財産を有している様子もなかったこと、依頼者Xさんは、前記のような電話に出て初めて、被相続人Aの債務の存在を知るに至ったこと、被相続人Aの生前から、依頼者Xさん自身は、郵便物を適正に管理する習慣がまったくなかったこと等の事情が存在したため、そのような事情を説明し、依頼者Xさんがその時点まで、債務の存在を知らなかったことには、やむを得ない事情があったと言える旨の主張を行ったところ、無事、申述期間の伸長を認めてもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。
その結果を、前記金融機関に通知したところ、今後請求は行わないという回答を受け、解決に至りました。
相続放棄は、前記のとおり、原則としては3か月間の制限期間内に行わなければなりませんが、ケースによっては、やむを得ず、その期間内に申述をすることができないといったケースもございます。
そのようなやむを得ない場合には、本件のように申述期間を伸長してもらうよう、裁判所に働きかけることが必要になりますが、どのような説明等を行えばよいかを検討するためには、一定の専門知識が必要になります。
身近な方がお亡くなりになった際に、法的手続きで慌てないように、ぜひお気軽に、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただければと思います。
その他の解決事例
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案
遺産分割調停遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。
被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:妹
兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。
財産の詳細が不明である兄弟間の相続において全て遺産整理業務を速やかに行った事案
遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:兄弟姉妹
独身で子供がいない兄弟が亡くなって相続が発生したものの、亡くなった兄弟の財産状況が不明な事案でした。また、他の兄弟姉妹である相続人の方も高齢であり、かつ、疎遠な関係であったことから、相続手続をとりまとめて行うことができる者がおらず困っている状況でした。
公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。
遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長男、長女等
生前、被相続人Aは遺言を残さないと言っていたにもかかわらず、相続人のうちの一人に極端に有利な内容の公正証書遺言が作成されているという状況でした。
残りの相続人は、あまりにもおかしいのではないかと、上記相続人に対して修正を求めていましたが、話を聞いてもらえないでいました。